
「デザイン思考における問題解決って何?」
「今までにできなかったような問題解決ができるなら、デザイン思考を使ってみたい。」
多くの人にとってデザイン思考はなじみのない概念であり、「問題解決」と一口にいっても、具体的な適用方法や効果がわかりにくいと感じるのは無理もないことでしょう。
デザイン思考は、「人の体験に焦点を当てた問題解決の方法」とも定義されます。問題を抱えている対象者の状況を深く理解し、相手にとって価値や意味があるように問題を解くことを重視するアプローチです。
問題を解くのであれば、デザイン思考がひとつの結論であり、デザイン思考程度を使いこなせないようなら話にならないと思ってください。
ダイエットといえばライザップ、テーマパークといえばディズニーランド、問題解決といえばデザイン思考、みたいな感じで、問題解決の分野ではそれほど中心に位置付けられているものなのです。
問題解決の伝統的な方法として、ロジカルシンキングがありますが、デザイン思考との違いを比較すると、以下のようになります。
【デザイン思考とロジカルシンキングの比較】
| デザイン思考 | ロジカルシンキング |
| ・解けるのは「人の問題」 ・人間と、人間が置かれている状況を理解した上で問題を解く | ・「仕組みや構造を作り、直す」もの ・構造に着目してその構造を分解したり構築したりして問題を解く |
デザイン思考とロジカルシンキングは、まったく別軸のものです。デザイン思考では人が置かれている状況を理解する必要があるのに対し、ロジカルシンキングは状況の理解がありません。
ただし、デザイン思考で「問題を抱えている対象者の状況を理解した上で、相手にとって価値や意味があるように問題を解く」の「解く」には、当然のことながら構造が必要になることがままあるので、ロジカルシンキングもできないとこれも話になりません。
ロジカルシンキングだけでは解けない問題が出てきた今、ロジカルシンキングという道具と、デザイン思考という新しい道具をうまく使い分けて、問題を解決していくことが重要になるのです。
そこでこの記事では、デザイン思考における問題解決とは何か、また実際の問題解決事例を通して、このアプローチの価値を解説します。
| この記事でわかること |
| ・デザイン思考は問題解決の道具の1つ ・デザイン思考を活用したことで問題解決に成功した事例 ・デザイン思考で解決できない問題の種類 ・デザイン思考の第一歩では適切な問題を特定するのが1番難しい ・デザイン思考で問題解決を進める際の注意点 ・デザイン思考でチームの問題解決能力を向上したいならコーチングがおすすめ |
より幅広い視点から問題に取り組むことを通じて、あなたが抱える問題の解を導けるようになるでしょう。
1.デザイン思考は問題解決の道具の1つである

デザイン思考とは、人の体験に焦点を当てた問題解決の方法です。問題を抱えている対象者の状況を理解した上で、相手にとって価値や意味があるように問題を解くという姿勢を大切にします。
我々は働いている中で「さまざまな問題を解く」という場面に遭遇しますが、デザイン思考はこれらの問題を解決するための道具の1つとして存在しています。
中には、デザイン思考に対して「革新的な解決策を生み出すアプローチ」のように勘違いしている人がいるようですが、デザイン思考はそのような流行りの思考法ではないのです。
デザイン思考は問題解決の1つの結論です。
| ・問題解決といえばデザイン思考 ・人の問題解決はデザイン思考なくしてできない |
このように認識してください。
ただし、どのような問題でも解決できるかというと、そうではありません。
デザイン思考で解決できる問題は、「人の問題」です。デザイン思考のプロセスでは、人の声を反映させることが重要なので、人の声を聞けない事象、問題は解決できません。
例えば、飛行機の工学的な問題をデザイン思考で解決することはできませんが、飛行機を操縦するパイロットと飛行機との間で生じる問題は解決可能です。
もっとわかりやすい例を挙げると、「体重100キロの人が70キロになりたい」のような「人の問題」を解決する際、100キロの現実と70キロの理想、この差を埋める問題解決方法を生み出せるのがデザイン思考です。
| <デザイン思考とロジカルシンキングの違い> 冒頭でご紹介したように、デザイン思考では問題を抱えている対象者の状況を理解する必要がありますが、ロジカルシンキングにはこれがなく、「与えられている問題がどのような構造で発生するのか」という分解しかありません。 【状況の理解】とは、例えば次のようなものです。 車から変な音がする場合、車を分解します。分解してみて結論が出ればそれで終了ですが、分解してみて結論が出なかったら、「これってどんな状況でどんなふうに使っているのですか?」と使用状況を改めて聞き直すかもしれません。 しかし、それだけでは状況を理解するのに全く足りていません。 そもそも、問題とされている「変な音がする」は、実際には使用者のただの妄想かもしれません。もしかしたら、精神的に不安定で、問題にならない程度の音が気になっているだけという可能性もあります。 このような状況をどう解釈するのかも含めて、単純な分解を超えて、人の体験や感覚を理解することが、デザイン思考では非常に重視されるのです。 |
2.デザイン思考を活用することで解決できる人の問題とは

デザイン思考とは、どのような仕組みでどのような結果が得られる思考法なのか、これがわかるとデザイン思考で問題解決するイメージがつきやすくなります。
ここでは、マシュー・サイド著「失敗の科学」の中に出てくる飛行機事故の原因を問題として解いた過程を例に挙げて、デザイン思考の仕組みと結果をお伝えしていきます。
1978年12月28日、ユナイテッド航空の飛行機が墜落しました。機長、副操縦士、航空機関士はいずれも経験豊富で、当日の飛行条件はほぼ完璧であったにもかかわらず起こったこの事故の原因は、「完璧な集中で時間感覚を失っていたこと」と「権威ある相手への萎縮」でした。
飛行機事故の概要は、以下のとおりです。
【飛行機事故の概要】 ・着陸体制に入り車輪を下ろした際、異音や振動とともにエラーが発生したことに不安を覚えた機長は、「問題を確認するまで飛行時間を延長したい」と管制に要請し、旋回の許可をとった。 |
この事故は、以下の2つのことが原因とされました。
| 事故が起こった2つの原因 |
| ・発生した問題にこだわった機長は時間感覚を失い、認識力が激しく低下していたこと ・航空機関士が何度も知らせた燃料切れの報告に対して、機長からは何の反応も得られなかったが、上下関係がチームワークを崩壊させ、それ以上強く言えなかったこと |
機長は時間感覚を失うほど問題を解決することに没頭してしまいました。そのことが原因で、正気に戻った時には燃料不足によりエンジンが停止していて、結果的に飛行機は墜落しました。
燃料が足りなくなることやエンジンが停止することを航空機関士が伝えているにもかかわらず、機長が反応していないことにも驚きですが、エンジン停止というとんでもない危機を目前にしても、航空機関士が機長に対してその事実を強く言えなかったことには信じられない気持ちになりますよね。
しかし、残燃料がなく、エンジンが停止する事実を伝えた結果無視された航空機関士は、もっと明確に伝えるべきか否かを苦悶した上で、権威ある相手を前に萎縮し、それ以上強く言えなかったのです。社会的圧力や有無を言わせぬ上下関係が、チームワークを崩壊させました。
この事件の失敗と誠実に向き合った航空業界は、「時間感覚を失うほど没頭している人間をどうやって現実世界に引き戻すのか」という訓練をやるようになりました。機長の補佐的な立場にあるクルーは、上司に自分の意見を主張するための手順を学び、訓練を繰り返すようになったとのことです。

参考書籍:マシュー・サイド著「失敗の科学」,ディスカヴァー・トゥエンティワン,2016年
この結果を見ると、デザイン思考の問題解決と酷似しています。
飛行機を工学的に設計するだけでは解けない問題があるため、飛行機は墜落しました。では、墜落を防ぐために何ができるかと考えたとき、導かれた解決策は、操縦士と副操縦士の関係をできるだけフラットにするための訓練を導入することでした。
これは、人間にとって意味があるように問題を解く、まさにデザイン思考の話です。
工学的にアラートなどを整備しても、人間は無視してしまったり、逆にエラーに気付けなかったりします。飛行機だけの問題だと人が登場しないので工学的な話になりますが、人間が登場してくると状況を理解して問題を解く、人の体験に焦点を当てて問題を解く、デザイン思考の話になります。
「集中して没頭しすぎて事故が起こるって、なんでそんなことになるの?」という状況を理解して、問題を解き、上下関係をフラットにする主張技術を取得する訓練を開発した。これがまさにデザイン思考という仕組みを使って問題を解決するということです。
<デザイン思考で問題解決するために飲み込まないといけない大前提> デザイン思考を使いこなすためには、我々人間はまず「状況の中に常に居続ける」ということを飲み込む必要があります。状況の中で体験し続ける、それが人間です。 小学生が1年生で学ぶ内容は中学、高校と続く流れにつながっています。その過程の中で、さらに新しいことを学び続ける、体験し続ける、それが人間であるということを大前提に置かなければいけません。 その大前提の上で、問題を抱えている対象者の状況を理解し、相手にとって価値や意味があるように問題を解きます。 例えば、バルミューダのトースターは、累積販売台数180万台の大ヒット商品で、最高に美味しい朝ごはんを食べ続けるために開発されました。 人間が最高の朝ごはんを食べ続けるには何をどうしたらいいのか、という状況を理解し、食感やニオイなどをいかに提供し続けられるか、と設計を考えた上で、そのための方法論としてトースターをどう提供するか追求して商品化したものです。 まさに人間中心にやって成功した例ですが、これが人間中心じゃなくなる(プロダクトアウト)と、成功していなかったでしょう。 人間中心じゃないと「会社にとって都合がいいように問題を解こうとする」ことが起きます。 売上がどうだとか、すでにある販路を使うとか、しょうもない話が優先されてしまうのです。しかし、そんな売上の話や販路の話なんて、顧客には全く関係ありません。にもかかわらず、そういうところを追求して商品を作ると、人の問題を見失いがちになって失敗します。 デザイン思考を使いこなしたいなら、我々人間は「状況の中に常に居続ける」ことを飲み込んだ上で、問題を抱えている対象者の状況を理解し、相手にとって価値や意味があるように問題を解く姿勢を持つことが大切だと覚えておいてください。 |
3.デザイン思考で解決できない、デザイン思考を適用しづらい問題の例
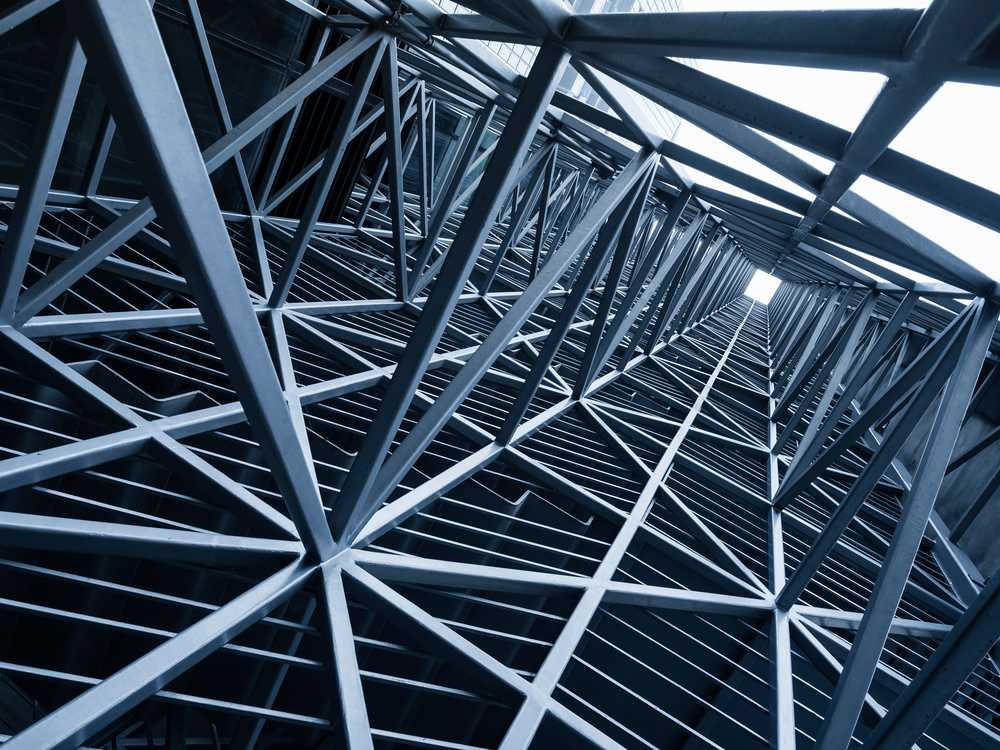
デザイン思考は人の問題を解決するための思考法であるため、人間が関与しないことには使えません。
この章では、この点について具体的なイメージが持てるよう、以下の2つの例を紹介します。
| ・デザイン思考では解決できない問題 ・デザイン思考を使えるけど適用しづらい問題 |
これらの例を通じて、デザイン思考の問題解決の限界についても理解を深めていきましょう。
3-1.デザイン思考で解決できない問題
先ほどもお伝えしましたが、人間が登場しない問題をデザイン思考で解決することはできません。
例えば、ダムの設計をするときに、「どれくらいの水を貯める必要があって、このくらいの水を貯めるためには、このくらいの強度が必要になる」といったような話にはデザイン思考は使えません。
これは全部計算の話です。
単純に水を貯めようとした時にどれくらいの圧力に耐えないといけないのか、そこで計算をしていくとなると、人間が登場する余地はありませんよね。余地がない、つまり人間が登場しないので、デザイン思考は関係ないのです。防波堤の高さをどうするかとか、そのような話も同様です。
人間が出てこないと使えない点が、デザイン思考の限界点と言っていいでしょう。
3-2.デザイン思考を適用しづらい問題
はじめの段階では人間が登場しない問題は、デザイン思考を適用しづらい問題と言えます。
デザイン思考は人の問題解決に使える思考法なので、人が登場しない段階では使えませんが、問題を解いている途中で人間が登場したら、その段階から使えるようになります。
このような状況では、「デザイン思考を使って問題を解くぞ!」とはじめから決めて問題解決に臨めないので、適用しづらい感じになるでしょう。
例えば、横浜にある東京電力のFP(フュエル&パワー)という火力電力事業の例で考えてみましょう。
FPは横浜に火力電力所を有し、発電プロセスで発生する余熱を利用したいちご狩りを運営していました。(※現在は閉園)
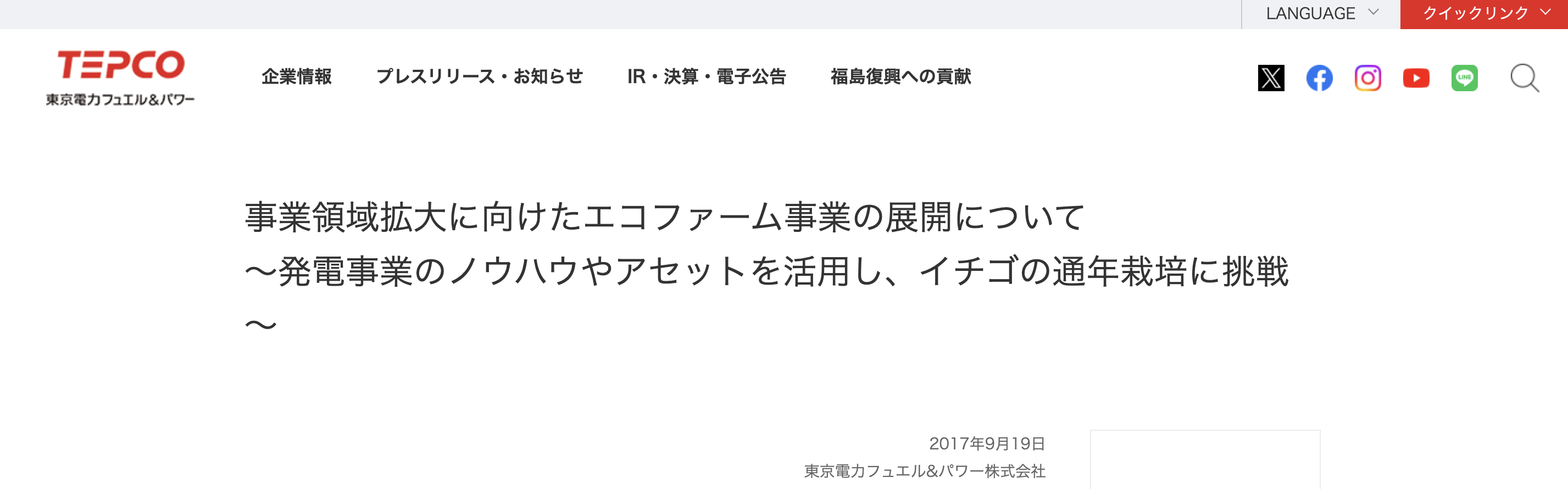
当初、FPは、火力発電所として何かを燃やし電気を生成する施設を他の用途に利用できないかと考えました。
発電プロセスで生じる余熱は100度未満で、そのため再利用が難しく、有効な活用方法が見つかりませんでした。火力を使って何かを作るという話だと、人間が出てこないので、デザイン思考では何ともしようがありません。
しかし、話し合いを重ねる中で「ただ熱だけを語っていたって仕方ない。そういうことじゃないよね。」という考えに至りました。
そこで、発電所周辺に住む人々との交流を促進しようと考えた際、人が出てくるので、彼らに何ができるだろうかと考えることができます。するとデザイン思考を適用できます。
この熱を使って周りにいる人たちに愛されたいとか、周りにいる人たちの役に立ちたいとかになると、全然違う発想が生まれ、「じゃあその熱で何かを育てたらいいんじゃない?」というアイディアが突如として生まれます。育てたらいいという話が進み、「いちご狩りとかどうかな?」となり、そこで火力発電の余熱を使ったいちご狩りのプロジェクトが始まったのです。
このように、人間が出てこないと如何ともし難いというのが、デザイン思考の適用しづらい問題と言えるところです。
4.デザイン思考の第一歩では適切な問題を特定するのが1番難しい

デザイン思考で具体的にどう問題解決するのかわからないという人は、最初のテーマ設定でつまずいていることが多いと言えます。
実際に仕事の問題解決でデザイン思考を活用する際は、デザイン思考に入る前のテーマ設定がとても重要です。
お掃除ロボットを使うときに、床においてあるものを取り除くなどの準備をしないと力を発揮できないように、デザイン思考もデザイン思考に入る前に準備が必要で、それがテーマ設定になります。
しかし、実際には大体の人たちが、テーマ設定することなく問題を特定するので、粒度が荒いままで「問題が見つかった」と言っています。
例えば、飲食店に飲みに行くときに、お店を決めるぐらいまでは「ここ」が決まったというレベルです。お店を決めて「ここ」が決まった上で、メニューは何を頼むのか「これ」が決まらないと、如何ともし難いです。メニューがたくさんある中で、最初の飲み物を全員ビールと決めつけて注文しても、「これ」に不満を持つ人がいて失敗してしまいます。「ここ」が決まっていても、「これ」っていう注文を外すと、それで終わりなのです。
だから「これ」を外さないために、相手に何度も確認することが必要になります。それが、テーマを設定して準備をしてから問題解決に入るということです。
テーマ設定をする際は、以下のことについてできる範囲でイメージしてください。
【テーマ設定で整理するべきこと】 ・検討内容概要 |
デザイン思考における問題解決の難しさは、そもそも解決するべき問題を特定できないことにありますが、上記のようなフレームを用いて整理してからデザイン思考に入ることで、よりスムーズに問題を特定してプロセスを回すことができます。
5.デザイン思考で問題解決を進める際の3つの注意点

最後に、デザイン思考で問題解決を進める際の注意点をお伝えします。
ここでお伝えする注意点は、以下の3つです。
| ・デザイン思考では5つのプロセスをこなせばそれで問題解決できるわけではない ・デザイン思考を使いこなしたいなら、使う環境にいる全員がデザイン思考について理解する必要がある ・理論を学んだ上で、実践への適応の仕方を練習する |
デザイン思考を使って問題解決できるようになるために、それぞれ把握していきましょう。
5-1.デザイン思考では5つのプロセスをこなせばそれで問題解決できるわけではない
デザイン思考を実践する際は、5つのプロセス(共感、問題定義、アイデア創出、プロトタイプ、テスト)を踏んでいきますが、5つのプロセスで重要なのは、共感からテストまでのプロセスをぐるぐる何十周も回すことです。
デザイン思考は、1周プロセスをこなしただけで問題解決できるほど、簡単なものではありません。
試作したものを試してもらい、フィードバックを得て再び試作品を作り直す。これを何度も繰り返していきます。
5つのプロセスは、共感、問題定義、アイディア創出、プロトタイプ、テストと順番がつけられていますが、繰り返す際は順番通りに辿る必要はありません。テストの結果を受けて、共感以外に戻る場合もあるでしょう。時には遠回りをしたり、寄り道をしたりしながら、粘り強く検証を繰り返すことによって、理想にたどり着くことができます。
デザイン思考で問題を解決することは、共感からテストまでを1度やりきればそれで終わりというものでは決してありません。これが、デザイン思考を使って問題を解決する上で本当に重要なことです。
5-2.デザイン思考を使いこなしたいなら、使う環境にいる全員がデザイン思考について理解する必要がある
デザイン思考は「道具」です。道具を使いこなすためには、その道具を使う環境にいる全員がデザイン思考について理解できている環境を整える必要があります。
道具は、全員が取り扱い方を理解していないと間違いや不都合が生じるからです。
環境を整えるとは、具体的に以下のようなことです。
【環境を整えるとは】 ・チームがデザイン思考について理解している |
まずチームがデザイン思考について理解していないと、「商品開発にデザイン思考を取り入れましょう」と言っても、「デザイン思考って何?」となってしまいます。これでは話が前に進まないので、チームでデザイン思考について理解するところから始めてください。
また、チーム全体がデザイン思考について理解できていないと、デザイン思考でアイディアを出しても評価の視点に相違が出ます。評価する人がデザイン思考を理解して問題解決に望まないと、正しい解決法を導けません。
また、前章でもお伝えしたとおり、デザイン思考は何十周もプロセスを回すものなので、時間がかかります。マネジメント層がそのことを理解していないと、「もっと効率よくやれよ」とか「時間がかかりすぎ」などと言われかねません。
マネジメント層を含めた環境全体でデザイン思考に対する理解を深めてから、デザイン思考を使った問題解決をはじめましょう。
5-3.理論を学んだ上で、実践への適応の仕方を練習する
デザイン思考を使って問題を解決するためには、理論を学んで知識を深めるだけでは不十分です。
知識として学ぶことと、それを実践に適用することは別だからです。
車の運転に例えてみましょう。赤信号は「止まれ」。これは理論です。では、赤信号を見て、止まるためにブレーキを踏む。これが理論を実践に適応するということです。練習していないと、止まらないといけないことはわかっているのに、赤信号を前にしてもアクセルを踏みっぱなしになってしまいます。
デザイン思考を使いこなすのも同じです。理論を学んでいても、実践への適用を練習していないと、デザイン思考を使って問題を解決できません。
また、ネットで検索してデザイン思考を学ぼうとしている人がいますが、やめてください。ネット上にはデザイン思考について誤った情報が溢れていて、信じられる記事が本当に少ないのが現実です。ネットの情報だけで理論を学ぶのは無理があります。
このことも踏まえた上で、理論を学び実践への適応の仕方を練習して、デザイン思考を使って問題を解決していってください。
6.デザイン思考でチームの問題解決能力を向上したいならコーチングがおすすめ

デザイン思考を実践で活用して問題解決したいと思っているなら、Beth合同会社のコーチングがおすすめです。
Beth合同会社のコーチングでは、デザイン思考を使いこなせるようになるために、デザイン思考のサイクルを回す過程はもちろん、問題解決の準備段階に当たるテーマ設定を伴走し、家庭教師的に教えながら一緒に問題解決を目指します。
自分たちでデザイン思考のサイクルを回して問題を解決できるようになることを目標とするので、物事を判断したり、考えた結果を文章でまとめてもらったりします。そのために、前提となるような物事を教えたり、いろんな考える観点を提供したりします。
また、デザイン思考を使うためのチーム内や組織の環境整備もお任せください。各種研修も行なっています。
<デザイン思考を問題解決に活用したいとお考えなら、Beth合同会社にお任せください>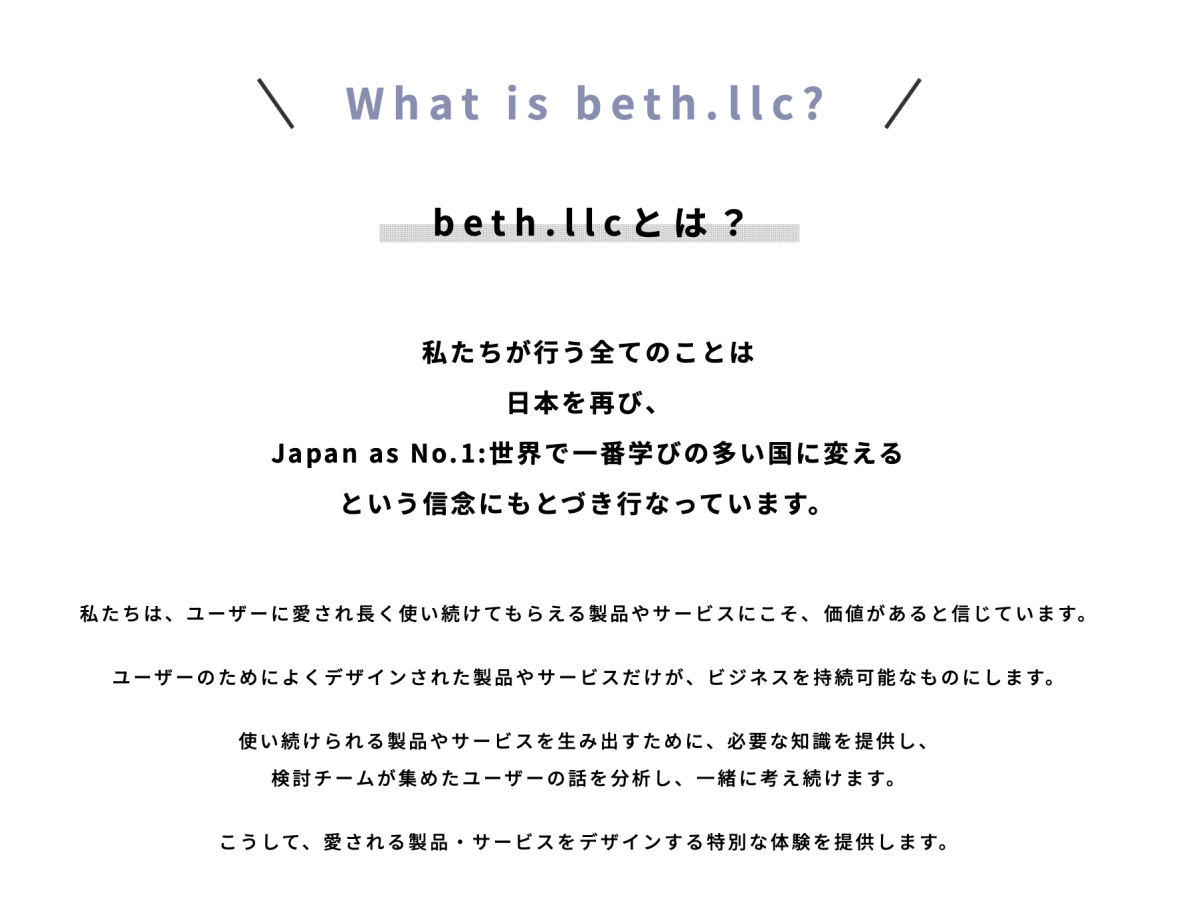 ご相談はこちらから ご相談はこちらから |
6.まとめ
本記事では、デザイン思考における問題解決についてお伝えしました。
最後にもう一度おさらいします。
デザイン思考とは、「人の体験に焦点を当てた問題解決の方法」で、問題を抱えている対象者の状況を理解した上で、相手にとって価値や意味があるように問題を解くという姿勢を大切にしている考え方です。
問題を解くのであれば、デザイン思考が1つの結論であり、デザイン思考程度使いこなせないなら話にならないと思ってください。
デザイン思考で問題解決したいけどなかなか前に進めない、という方は、ぜひお気軽にご相談ください。


 出典:
出典: